あしたのジョー Ashita no Joe: Fighting for Tomorrow
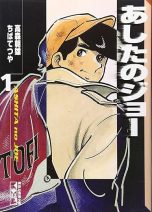
このマンガのレビュー
「今日に至るまでの漫画界には、大きく2つの流れがある。その源流にいるのが、手塚治虫とちばてつやだーー」。僕にそう話してくれたのは、89年の連載開始からいまもなお現役で連載されるボクシング漫画『はじめの一歩』作者の森川ジョージ氏だ。そしてもちろん、森川氏の源流にいるのはちばてつやであり、氏が生み出した『あしたのジョー』から少なからぬ影響を受けていることは疑う余地もないだろう。90年代を幼少期として過ごした僕の世代の人たちで、『あしたのジョー』の物語を最後まで読んだことがある人はきっと多くはいないと思う。しかしながら、「燃え尽きたぜ…真っ白にな…」という言葉とともにリングのコーナーで真っ白になったジョーの姿はあまりにも有名であり、このシーンを聞いて『あしたのジョー』を思い浮かべる人は少なくないはずだ。ファンタジーの世界や人間社会について俯瞰で見つめ我々に気づきを与えてくれる手塚治虫であるならば、ちばてつやは漫画の黎明期において一人の人間の生き様を描くことでその時代を映し出すことのできる稀有な漫画家だったのだと思う。戦後最大のヒット漫画と言われる同作ではあるが、いま読んでも色褪せるどころか鮮やかすら感じさせられるのは、矢吹丈の生き様がそこに刻まれているからかもしれない。
このレビューを書くために、ぼくは本棚にあった文庫版の第8巻を無造作に手にとって家を出た。そして、骨伝導イヤフォンで尾藤イサオの「あしたのジョー」を聴きながら、井の頭線のなかでジョーVSカーロス戦を読んだ。パラパラと暇つぶしにめくれない凄みがあるこの作品を読んだのは、じつに10年ぶり。ぼくが大学教員になる前にトーキョーで会社員をやっていたとき以来だ。『あしたのジョー』は、舞台がそうだからなのかもしれないが、トーキョーで読みたくなる。
髀肉の嘆、という中国の諺がある。三国時代に蜀の劉備が長い間戦場に行かなかったせいでふとももの肉が肥え太ったことを嘆いた説話にちなんで、手腕を発揮することなくむなしく過ごす時を嘆くことの意味だ。自分なりに一生懸命生きてきたはずの十年だったけれども、カーロス戦を読むとなんだかそれでも足りなかったんじゃないか、もっとストイックにやれたんじゃないかという心地がしてくる。「俺らにゃ荒野がほしいんだ」と尾藤ボイスが耳元で響く。キレイなビルと外国人観光客とくたびれた中年のぼくが同居するシブヤで。ドヤ街に住んでいたとか、食うに困った経験がなくても、なぜかぼくらはジョーに自分を重ねるし、都市の中にいて最も都市的なものから遠い存在に惹かれてしまうのだ。
カーロス戦の後、ジョーは紀ちゃんと懐かしの公園に行く。そこで紀ちゃんからボクシングを辞めたらと尋ねられると、ジョーは「負い目」があるからいまさらやめたいとは言えない気がする、と想いを吐露する。ジョーが力石やカーロスから「負い目」を受け取ったしまった。それが自身を駆動するのだと。ぼくもそうだ。「あしたのジョー」を読むたびに、そこから「負い目」を受け取って、このままじゃいけないと駆り立てられる。それは等価交換が当たり前の世界における、人間の本質からの抵抗なのかもしれない。
本作は、主人公「矢吹ジョー」一人の物語のみならず、まさに戦後経済成長期を経験した若者世代全体の気持ちを反映する当時の格差社会の日本のリアリティへの注目の訴えといっても過言ではない。ちばてつや先生が見せる戦後に大いにかつ急速に発展してきた大都会としての東京のイメージを裏切る下町のスラム街の対象的表現は物語の背景だけではなく、作品のエッセンスそのものだ。アンダーグラウンド社会に暮らす貧困層はこの変わりつつある新時代では何を目指すべきか?そのようなテーマを取り上げる画期的な描写は団塊世代の心を刺さり、あまりにも印象深くゆえに未だに他のあらゆるメディアでも名場面のオマージュが現在見られるように一般社会に根付いている。
キャラクターの辛い生き様の部分も遠慮せずに描くちば先生は同時にシンプルでありながら表情をきわめて繊細で優しそうなニュアンスを保つからこそ、登場人物が社会の逸脱者であっても読者の共感を得られる絶妙な普遍性を持っている。
日本ではあまりにも社会現象を巻き起こした名タイトルになっており、さらに欧州などでテレビアニメ版も数十年前から放送されているにもかかわらず、半世紀以上英語圏においてはほとんど知名度が無く、2024年には57年もの時を経てようやく英語翻訳版が初めて登場した。今後もかつての日本の心を代表する名作はさらに世界的な認知度が上がることが期待できそう。