はだしのゲン Barefoot Gen
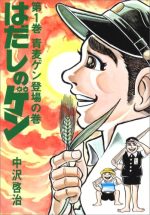
このマンガのレビュー
僕がまだ小中学生だった1990年代は、戦後50年を迎える年代もあり戦争を題材にした物語を目にする機会が多かった。そのなかで、いまでも記憶に残っているのは金曜ロードショーで度々目にした『火垂るの墓』と小学校の図書館で繰り返し読んだ『はだしのゲン』くらいだ。『はだしのゲン』は、原爆が落とされた広島の地でたくましく生き抜く少年・中岡元の物語である。物語は原爆が投下される少し前から始まるが、投下された直後に元と母親が家屋に下敷きになり身動きが取れない父親と姉弟が火達磨になる様子をなすすべもなく見届けるさまや、そこかしこに身体中が焼けただれた人が倒れ、生き残った人たちも気が狂っていく様子に目を背けたくなる。およそ現実に起こったこととは思えないほど凄惨な世界が眼前に広がっていた。非国民や鬼畜米兵、ヒロポンなど、この本から教わった言葉も少なくない。読むだけでトラウマを植え付けられるような悲惨な描写が多くあるにもかかわらず、『はだしのゲン』がこうしていまも注目されているのは、戦争の残酷さを伝える資料性の高さだけでなく、底抜けに明るくて優しい元をはじめとした登場人物たちのドラマに魅了されるからなのではないだろうか。戦争を知らない僕たちにとってはもはやファンタジー世界のように読めるからこそおもしろいのも事実だが、これがかつての日本で実際に起こり、そしていまも世界のどこかで現実に起こっていることを忘れてはいけない。こうした作品を生み続け、後世に語り継いでいく責任があるのではないだろうか。
今でこそ学校の図書室に漫画が置かれる事は(多く無いにせよ)普通にあるが、以前は「はだしのゲン」が図書室に置いてある唯一の漫画として有名だった。
「はだしのゲン」は作者中沢啓治の自伝的作品であり、主人公の中岡元は作者の分身である。後に文章で書かれた自伝と照らし合わせると、物語の最初の数話はほぼ実話だ。
そうした原爆の惨禍だけでなく、当時の世相や作者自らの思いがダイレクトに描写されている事もあり、近年図書室から撤去する学校も出て来て議論を呼んだが、中沢は没後の2024年にアメリカで最も権威のある漫画賞「アイズナー賞」の殿堂入りを果たした。
それは「原爆ドーム」が、終戦直後には取り壊すべきという声もあったが保存されて、後に世界遺産に認定された事とかぶって映る。
中沢の絵柄と演出はとても濃密で「漫画」というよりは「劇画」であり、現在の漫画表現からすると時代遅れとも映るかもしれない。それでこの作品が敬遠される向きもあるが、それはとても勿体ない事である。
その濃密な筆致で描かれる「原爆の惨禍」や「反戦」は確かにこの作品の根源ではあるが、もう一つ「若者の成長」というテーマがあり、被爆した焼け跡から這い上がる少年少女たちの青春物語でもあるのだ。
そしてもともと週刊少年ジャンプで連載がスタートした事もあってか(1973年~1974年間連載された後「市民」「文化評論」「教育評論」各誌にわたり、1987年まで連載)漫画としてのエンタメ性も忘れずに描かれている。
つまり語弊を恐れずにいえば、この「はだしのゲン」はとても「面白い作品」なのである。
戦後80年。もしこの作品を敬遠している人がいれば、80年前の「時代劇」としてこの作品に触れ、その上で実際におきた原爆の惨禍や、戦後の歴史について改めて考えてみるのも、ひとつの読み方としてあってもよいと思う。
中沢啓治による『はだしのゲン』は、広島への原子爆弾投下を描いた自伝的マンガである。戦争の悲惨さや平和の尊さを訴える作品として、学校の図書室に配架されていたり、日本だけでなく世界中で翻訳出版されていたりする。中沢自身が原爆の被爆者であり、その体験をもとにした作品であるため、単なるフィクションを超えた強烈なリアリティを持って描かれている。原爆で焼け死ぬ人間の姿や擬音語「ギギギ…」など、読む人によっては気分が悪くなる可能性すらあるほど強烈なインパクトを有したマンガである。戦争に苦しむ中で、それでも希望を見出そうとする者もいれば、自己中心的な行動をとる者もいて、他者を助けようと奮闘する者もいるなど、様々な人間模様が描かれている。戦争という極限状況における人間の多面性が浮き彫りにされており、読者は単に戦争の悲惨さを学ぶだけでなく、戦時下における人間性についても深く考えさせられる。2025年は昭和100年にあたり、ちょうど終戦80年にあたるので、今一度『はだしのゲン』を読み直してみてはいかがだろうか。世界においては現在においても戦争が生じている国・地域がある。戦争の悲惨さ、平和の尊さを忘れないためにも、後世に伝え残していきたいマンガ作品のひとつである。
誰もが知っている、広島に投下された原子爆弾の被害を受けた少年の青春物語です。実は、原子爆弾の投下と終戦は物語初期の出来事であり、その後はゲンが戦後を生き抜いていくことを描いています。暴力や薬物依存など、戦争被害そのものではないものの戦後の復興期に社会に広がった問題を隠さずに描いたところに、広いテーマ性というこの作品の特徴が現れています。
もう一つの特徴として、主人公のゲンは、家族にそっくりな人物との出会いが繰り返し訪れます。ある日一瞬で奪われた家族への執着が、ゲンに対してそのような認識を起こさせたという面もあるのではないでしょうか。
私は、曽祖父の代が当時広島市に住んでおり、私自身が被曝者の子孫であることを認識してから、この物語をより鮮明に感じられるようになりました。近年、一部の小学校の図書館からの撤去が話題になりましたが、今も子どもたちに読み継がれています。世界的に戦争への抵抗感が下がってしまっているかのような2020年代において、改めて読み返されるべき漫画だと思います。
『はだしのゲン』は、原爆投下前後の広島をたくましく生き抜いた中岡元ことゲン少年の物語である。作者の中沢啓治は1939年広島生まれ。女手ひとつで中沢ら3人の子どもたちを育てた母の死をきっかけに、中沢は原爆に題材を取った作品を書き始める。先行マンガ誌を抜き100万部を超した『少年ジャンプ』で、1973年から連載されたのが『はだしのゲン』である。
現在の日本では、往時を自身の体験としている人たちも少なくなり、また、ウクライナやパレスチナの情勢、中台や日朝の関係などから「戦争」の意義も相対化されている。「悪い戦争ばかりではない、良い戦争や必要な戦争もある」という主張は説得力を強めて広まっており、「原爆と戦争の恐ろしさを子どもたちに伝えて平和を希求する」という中沢が本作品に込めた想いも伝わりにくくなっている。さらには「エピソードが事実ではない」「思想が偏向している」「子ども向けとしては描写が残酷すぎる」という批判も年々強まっている。
本作品は、さまざまな言語に翻訳されて、諸外国でも出版されている。京都国際マンガミュージアムで見ることもできる。その多くは、原爆投下の日に、母が出産し、その子に「おまえが大きくなったら二度とこんな姿にするんじゃないよ」と語りかけるところで終わっている。放射線の人体への悪影響や、米軍占領下の不条理、被爆者差別などはカットされている。そのせいか「戦時中、日本は他国に対してひどいことをしたのだから、原爆投下は当然の報いである」という角度からの読解も外国人からはされてもいる。
しかしながら、中沢の被爆者としての当事者性はゆるがない、体験をマンガとして昇華する作家性も確かなものである。ゆえに、中沢の想いに対するスタンス、政治的なポジションの如何にかかわらず、ゲンの成長という物語の骨子に目を向け、『はだしのゲン』全体を読む人が、世界中に増えたなら、中沢と作品の評価は新たになるはずだ。
『はだしのゲン』は意外にも1973年「週間少年ジャンプ」の連載作品だ。もともと原爆被爆者として差別を避けるべく広島や原爆と無縁のマンガばかり描いていた中沢啓治氏が放射線のために母の骨が灰となってひとかけらも残らなかったことをきっかけに自伝を遺すことを決意。その33歳になってからの遅咲きの自伝的作品「おれは見た」が今の「はだしのゲン」であり、ギャグ・ラブコメ志向が強まる1970年代半ばの少年誌では当然ながらアンケート人気も低迷。編集長長野規の思い一つで限界まで連載された。
その内容の衝撃さは誰も忘れられないだろう。私も小学生のときに皮膚がただれる恐怖と、目の前で父姉弟が焼死する衝撃のシーンはトラウマである。ダンテ『神曲』にもみるように人は地獄を可視化することによってはじめて倫理を実感し、社会的秩序を志向する。私も『はだしのゲン』をみたことで原爆や戦争のリアリティを追体験し、それらが近寄りがたく軽口で批評するたぐいのものではないという「原体験」となっている。
集英社をして「単行本になると社名に傷がつく」と言わしめるほど物議をかもした本作が、日本共産党系出版社で再び連載が続き、汐文社で出版までもっていったことをもって、日本の出版産業がいかにその分散的な産業構造によって文化をつくりえたのかを実感する。これはマンガの域をこえた文学であり、「残すべきものである」と今やだれもが思うものだが、1970年代においてすらそう思われていなかった、ということを我々は胸に刻んでおくべきだろう。本作があるのとないのではマンガというメディアの「重み」が全く違っていたことだろう。