ゲゲゲの鬼太郎 GeGeGe no Kitaro
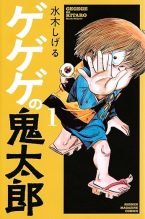
このマンガのレビュー
数年前、鬼太郎の原作を初めて読んで、未知の感覚に襲われた。
“底冷え”というか”虚しさ”のような。擬音描写を読んでもまったく音を感じない”静寂”で、それでいて直接脳内に音が届いてるような。ジト〜っとした空気が漂っているのにカラカラ。なんとも言語化しにくい奇妙な体験をしたマンガは後にも先にもこのシリーズだけ。
幼い頃に観ていたアニメの鬼太郎は、あの世とこの世の狭間で、悪い妖怪を人間の為に退治してくれるヒーロー…だが、原作を読み進めるごとに鬼太郎の立場は決して我々人間にとって都合のいいものではないことが解った。
彼はあくまで”妖怪族”の末裔で人間ではない。多くの場合、人間の生命を悪戯に使う妖怪たちの暴走を収め、妖怪と人間の間に起こる事件を解決することが彼の役目だ。
しかし時に鬼太郎自身が、素行の良くない人間と出会した際には妖怪としての戒めを見舞うこともある。
また事件解決の後には、数分前まで救済を懇願したはずの人間たちの態度の代わり様に肩を落とし、独りごちながら帰路に着くことも。
古くから”妖怪”とは、人間の欲望や念の具現化した姿と言われている。他者を騙し金を毟り取ってみたり、永遠の若さにすがり生命力を吸収してみたり、と作中に登場する妖怪はさまざま。
では、鬼太郎はいったいどんな感情の妖怪なのだろうか?それはきっと”平和な日常”だ。
南方諸島での戦禍を生き抜いた水木しげる先生の願望そのものなのかもしれない。人は愚かで、感情に走り、つい直前の失敗も忘れてしまう。
水木先生は鬼太郎を通して世間に訴えかけ、目玉おやじの言葉で諭しつつも、読者諸君もねずみ男のような欲に塗れた部分を持つ生き物なんだ。と教えてくれているのだろう。
しかし、作中でよく見るように鬼太郎の声は決して人間たちには届いてない。届いたところで長持ちはしないのだ。
妖怪マンガの元祖とも言うべき『ゲゲゲの鬼太郎』は、妖怪マンガの第一人者である水木しげるの作品である。マンガ作品は第25回(1996年度)日本漫画家協会賞・文部大臣賞を受賞。また、テレビアニメ第6シリーズは第57回ギャラクシー賞にて、アニメ史上初となる特別賞を受賞。さらに、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は第47回日本アカデミー賞・優秀アニメーション作品賞を受賞。世界各国で翻訳出版されたりアニメ放映されたりしている。まさに日本を代表する妖怪マンガ・アニメと言えよう。アニメ化、ドラマ化、映画化、小説化、舞台化、ミュージカル化、ゲーム化など様々なメディアミックス作品が存在するが、おそらくアニメ版が最も有名であろう。アニメ版は知っているけれど、原作マンガは知らない、という若者も多いと思うので、是非とも原作マンガにも注目してもらいたい。最初はアニメとのギャップに戸惑うかもしれないが、読んでいくうちに慣れてくるどころか、ハマってしまうこと間違いなしである。ちなみに、トキワ荘に住んでいたわけではなく、経営していたアパート「水木荘」からペンネーム「水木しげる」にしたということである。
主人公の鬼太郎を取り巻く、目玉おやじ、ねずみ男、ネコ娘、砂かけばばあ、子泣きじじい、ぬりかべ、一反もめん、など個性豊かな妖怪たちも魅力的である。鬼太郎の必殺技も独特で、髪の毛針、妖怪アンテナ、指鉄砲、ちゃんちゃんこ、リモコン下駄、など記憶に残るものばかり。歴代のアニメ主題歌も印象的で、特にアニメ第3期のOP曲「ゲゲゲの鬼太郎」(吉幾三)は一度聞いたら忘れられないインパクトがある。鳥取県境港市に行けば、水木しげるロード、水木しげる記念館、鬼太郎列車などがあり、妖怪好きの子どもは大喜び間違いなし。最寄り空港の愛称は、なんと「米子鬼太郎空港」。空港に名前がついたマンガの主人公はゲゲゲの鬼太郎と名探偵コナンくらいである。
最近、ゲゲゲの鬼太郎が流行っている。「ゲ謎」映画の大ヒットがすごいのだ。目玉おやじがイケメンになり、愛でられることになるとは夢にも思わなかった。
水木しげるは1922年生まれ。第二次世界大戦で徴兵され、のちに帰国して漫画家となり、昭和史やラバウルでの戦争経験を作品として発表した。2024年にリニューアルオープンした水木しげる記念館は、水木しげるの戦争体験紹介に重点を置いている。僭越ながら、記念館の構成や最初の企画展は手伝わせていただいた。
貸本漫画で最初に発表された『鬼太郎の誕生』は、大筋は同じだが、血液銀行の社員が鬼太郎をみつけ、その後どうするのかで出版された4本ごとに話の筋立てが違っている。
水木しげるはねずみ男がお気に入りだったそうだ。インタビューでは彼がこの作品の味わい深さを作っていると発言している。彼を強烈に印象付けるのは、金に汚くて都合が悪くなると逃げるというその人間らしさだ。ねずみ男だったら、TikTokやトランプ大統領をどう評するのだろうか。
鬼太郎作品は数が多いので、自分の好きな鬼太郎を探すのもおもしろい。「おばけナイター」や、妖怪好きなら知っている「深大寺のすき焼きパーティー」も名作だ。境港やラバウルで数々の不思議な体験をし、東京に出てからも夜中に墓場を散歩した、と自身でも記している水木しげるならではの世界観だ。「新ゲゲゲの鬼太郎」では、鬼太郎の背が高くなり、服も現代的だ。出版社からの要望でちょっとアダルトになったそうだが、そんな急な変わりようもユーモアたっぷりで、楽しい。
2024年の夏に開催された「行方不明展」、2025年には「150年」という展覧会が20代にずいぶん人気になった。自分でも見に行ったが、確かに凄い人だった。清潔で安全で明るくなった都市の生活では味わえない感覚を、本能が取り戻せと言っているのかもしれない。鬼太郎は、そんな暗くて、怖くて、湿った感覚に溢れていると思う。