ドラえもん Doraemon
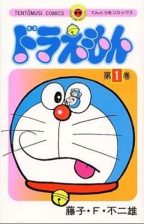
このマンガのレビュー
説明するまでもなく子供から大人まで人気の高い作品である。その背景は、「ウメ星デンカ」という未来という非日常における日常生活を描いた作品であったがあまり人気が出ず、ドラえもんで未来からやってきたロボットが日常生活で未来の道具を持ち出して問題を解決するという設定に変えたところで大ブレークをすることになる。
更に1968年の前作「21エモン」も人気が今ひとつだったが、その作品に出てくる未来のアイデアは、ドラえもんの中でも四次元ポケットから出てくる秘密道具に生かされている。
「21エモン」「ウメ星デンカ」という当時評価が低かった作品のアイデアを活かしたことで生まれたのが「ドラえもん」であると考えると非常に面白いトライアルであったと感じる。
ちなみに宇宙パイロットに憧れる21エモンは江戸幕府成立当時に創業したホテル「つづれ屋」を父親である20エモンから後を継ぐようにとボーイで働かされるという設定である。
そう考えるとドラえもんは22世紀からやってきた22エモンということになる。
作品を越えて、アイデアを引き継がれた「ドラえもん」は作者である藤子・F・不二雄の集大成とも言えるだろう。
藤子・F・不二雄は「『ドラえもん』の通った後はもうペンペン草も生えないというくらいにあのジャンルを徹底的に描き尽くしたい」と語っていた。その望みは藤子Fの他界によって絶たれたかに見えたが、1300話以上に及ぶ『ドラえもん』各話のバリエーションの豊かさをあらためて確認すれば、きわめて高いレベルまで達していることがわかる。
そんな『ドラえもん』を「現代の民話」と喝破した人がいる。その比喩に触れたとき、言いえて妙だと思った。藤子F自身が『ドラえもん』のルーツとして「グリム童話」「西遊記」「アラビアンナイト」など民話由来の作品をあげているし、『ドラえもん』という作品の様式・構造や時代の超え方を見ると、まさに「現代の民話」という比喩が的確なものだと納得できる。民話とは口伝えで連綿と後世に語り継がれてきた物語だが、『ドラえもん』はマンガという手段で世代を超えて読み継がれている。
『ドラえもん』に「現代の民話」という比喩が相応しいとしても、そういう比喩の手を借りる以前に『ドラえもん』はマンガらしいマンガの代表例である、と付言しておきたい。マンガの一つの典型でありスタンダードであるような作品だと思えてならない。少なくとも、1960年代後半からそれ以降に生まれた世代のかなりの人々にとって、『ドラえもん』はそういう存在たりえているはずだ。われわれの成長過程の中で普通にそばにあった作品であり、マンガへの入口の機能を持ち、みんなの共通体験になっている。
ドラえもんはのび太を助けるため未来の世界からはるばるとやって来た。私のところにも来てほしいと思ったが、もちろんその夢はかなわなかった。しかし私には、われわれには、物心がついたときから『ドラえもん』のマンガが身近にあった。『ドラえもん』を読むことが日常的な救いになってくれたのだ。
ドラえもんは、私にとってインフラのようなものである。スマホとかWi-Fiのようなそこにあることが当たり前の存在。それがドラえもんである。
ドラえもんは2112年9月3日生まれ。手塚治虫の火の鳥に出てくるロビタは2900年くらいなので、火の鳥の世界線よりドラえもんの世界はテクノロジーが発達している。手塚治虫に憧れ、デビュー前から手塚治虫と文通していた藤子・f・不二雄。我孫子元雄と2人、富山県から上京し、藤子不二雄名義で活動していた最初期は、手塚治虫が仕事場にしていたトキワ荘の部屋を敷金なしで譲ってもらった逸話が、藤子不二雄Aの『マンガ道』に残されている。
てんとう虫コミックスで全45巻、映画化された長編は別物として発行されている。長編の中ではまだ作者がご存命中の作品である1992年公開の「のび太の雲の王国」を紹介したい。
雲の王国は、その名の通り雲に乗って、雲で生活できる場所を作るのである。なんて夢があって楽しいのだろう。昨今のテクノロジーの発達はめざましいが、どうも楽しい気持ちにならない。人工知能が人間を支配するとか、暗号通貨のマイニングによる環境破壊だ、とか、SNSでフェイクニュースが流れて政治に悪用されている、闇バイトが秘匿性の高いアプリで横行している、とかうんざりすることばかりだ。ドラえもんは、そういうディストピアをしっかり無くして、みんな反省してやり直すというユートピアに溢れている。間違いや人の弱さを受け入れる許容性を持っている。
欧米圏では弱い子供が主人公だと受け入れられないとかで、いまだに認知度が低いと聞く。それは浅はかな捉え方だろう。強さとは、身体的な見た目や経済条件だけでは決められないことが、いつか伝わることを願う。
わたしは大学の授業でSF思考(SFプロトタイピング)とマンガのストーリーづくりの手法を用いて、未来を生きる人びとのストーリーを考えることを通して、未来社会のあり方と課題を議論するワークショップを行っているが、「ドラえもん」は物語づくりおよびキャラクターづくりのよいお手本として活用している。
第一幕:のび太はジャイアンとスネ夫に無理難題を吹きかけられる。
第二幕:ドラえもんが未来の道具でその難題を解決する。しかしながら話はそこで終わらず、のび太はその道具を悪用してイタズラをする。
第三幕:悪用も永くは続かず、のび太は失敗し懲らしめられる。
以上が「ドラえもん」の基本的な物語構成であるが、シンプルながらも極めてわかりやすい三幕構成となっている。主人公のび太、相棒ドラえもん、対立者ジャイアンとスネ夫、時には支援者としてしずかのように、キャラクターの設定・立ち位置も極めて明確である。学生に物語づくりを指導する際に、「ドラえもんの第二幕はこういう展開だけど、あなたのストーリーならどう当てはめる?」「あなたのこのキャラクターはドラえもんのキャラクターでいうと誰にあたるの?」と問えば学生も良くこちらの意図を理解してくれるのである。
「ドラえもん」のストーリーは「課題」が解決したあとも万事全て良しではなく、新たな課題が表れてくること、ある課題解決法の適用にあたっては「のび太のイタズラ」のような想定外のリスク(それゆえのび太は「最強のベータテスター」でもある)をいかに気付いて評価するかが重要であることを気付かせてくれる。特に後者については想定外に思いをはせるSF的発想が鍛えられるのである。
「ドラえもん」は先が全く見通せないVUCAな現代社会において先を見通す能力を涵養する格好の「学習マンガ」と言えよう。
ザ・国民アニメとなった『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄氏が「ずっと子供の心を失わなかった」天才から生まれている。1933年生まれのF氏は17歳でA氏とコンビを組み、1951年には漫画家デビューを果たした早熟のマンガ家で『ドラえもん』連載開始時1969年はすでにデビュー18年、36歳になっていた。F氏の短編集をみればいかにそのストーリーテラーとしての才能が傑出し、複雑な哲学や歴史の深い大人の世界を描くことに長けていたかを実感できるが、そうした武器をすべて封印し、あえて幼稚園から小学校1~6年、中学校まで1学年ごとに分かるようにドラえもんを描き分けていたことにその凄みを感じる(当初ドラえもんは1977年創刊『コロコロ』ではなく、1969年から学年誌ごとに連載、1年たったころにドラえもんが未来に帰るという“卒業”も含めた1年サイクルの子供向け短編マンガ集だった)。
まるで漫画界の池上彰だ。自分自身が知って広げることは意外に簡単で、知ってしまったあとにいかにそれを知らない後塵が分かりやすく辿れる道を作るかということは困難を極める。モチベーションとしても。それを30代、40代、50代としてのマンガ家、ストーリーテラーとしての円熟期に、人生を費やし、最後まで書き続けたF氏は、日常生活が破綻した“天才漫画家たち”と一線を画し、よき父であり、家族と長い時間も過ごしていたことが藤子・F・不二雄ミュージアムを通じても実感できる。子供の目線に立ち戻ることを、ずっと繰り返し続けていた人なんだろうと思う。柔軟さを失えば、あれだけの“発明品”を量産することなどできないだろう。