日出処の天子 The Emperor from the Land of the Rising Sun
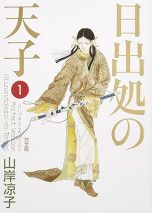
このマンガのレビュー
これは歴史マンガであって歴史マンガだけでなく、ヒューマンドラマであってヒューマンドラマだけではない。すべての完成度がここまで高い物語は、日本に、世界にどれだけあるだろうか。そう表現するのに一ミリも躊躇しないでおすすめできるのが「日出処の天子」である。主人公は聖徳太子と蘇我蝦夷の2人である。この2人は教科書にも出てくるので、名前くらいは見たことがあるだろう。聖徳太子は遣隋使を当時の中国に送り、その時代アジアの中心的な国である中国に「日出処の天子、書を日没する処の天子に致す」という挑発的な手紙を送ったことは有名である。他にも十七条の憲法や冠位十二階の制定、仏教の振興につくした人物と教えられる。逆に蘇我蝦夷は、蘇我家の棟梁として専横をふるい、息子の蘇我入鹿が殺されると自らの邸宅に火を放ち自害した。その程度が教科書に紹介されている。ただ、その「結果」に至る背景には何があったのか。そこに迫るのが本作である。そう書くと、歴史の学びになるマンガなのか?と思うかもだが、そうではない。この作品の本質は、私は「人は自分を愛せなかったときに、誰かの愛にすがりつく。その愛が”絶対”に報われないと知ったときの絶望。絶望の先に人は行動を起こすのではないか」ということだと思う。人は誰かのために生きることができるのか。それとも自分のために行動するのか。運命と愛、家族と恋、野望と欲望、人間の生きとし生ける「営み」のすべてが入っているのがこの作品である。もしかしたら最初は絵にとっつきにくさを感じる方もいるかも知れない。しかし、この絵でしか演出できない山岸凉子先生の魅力に、すぐに取り憑かれることを保証する。それどころか美しさにひれ伏すことになるだろう。死ぬまでに一度、そして可能ならおとなになる前や、大きな壁にぶつかる前に、読んでほしい作品である。
予備校の先生に「これと『あさきゆめみし』は読んでおけ」とすすめられたのがきっかけだ。正直、聖徳太子といえば子どもの頃に見た一万円札の肖像、あるいは歴史教科書の中の偉人ぐらいの認識。まさか漫画でこんなにも魅力的に再構築されるなんて思ってもみなかった。
いたるところに好きな場面しかないけれど、今ふと思い出したのは、皇子が崇峻天皇に呼び出されるシーン。長雨を降らせた“責任”を取れと言われてるのに、皇子はなかなか行こうとしない。ようやく行ったタイミングで雨がパタッと止んでしまい、天皇サイドは何も言えなくなってしまう。でもあとになって、それは皇子が空の様子を見て「もうそろそろ止むだろう」と理詰めで読んでいたというリアリティ! 神秘と現実を絶妙にミックスしたこの“手口”に、痺れる。
サブキャラで好きな人もたくさんいるけれど、今になると蘇我馬子。一見「ガハハ」なおじさんっぽいんだけど、政争の嵐をしたたかに渡り歩くバイタリティがかっこいい。皇子ともお互いに利用してやろうというある種の歪んだ信頼関係があるのがたまらない。こういう脇役が厚みを持って動いているおかげで、厩戸皇子の神がかったオーラがいっそう際立つ。
あとは毛人との“イチャイチャ”が挟まれると、今でいうところの“尊さ”全開でかわいすぎる。厩戸皇子と蘇我毛人の距離感にドキドキさせられる少女マンガってどういうこと? と当時は衝撃を受けたけれど、今になっていれば王道ですね。
今はだいたい十年に一度、記憶がほんのり薄れた頃合いに再読しては、「やっぱりこの漫画は史実でしかない!」と頑なに信じ込むくらいには大事にしている。山岸凉子が作り上げる飛鳥時代の息遣いは、創作というよりも、当時を「見てきた」感覚がある。何を言われようと、これは僕にとって立派な“史実”そのものだ。
本作は高校3年生の時、共通一次試験で日本史選択だった自分にとって、飛鳥時代の歴史の理解に役立つとの同級生女子の言葉を受けて初めて読んでみた。最初は、独特の四角いフキダシや絵柄がどうしても苦手でなかなか読み進めなかったのだが、読んでゆくうちに、歴史漫画というよりも、聖徳太子(厩戸皇子)の強いようで繊細なキャラクターに魅了されてゆき、もはや受験勉強はどこへやらと全編を何度も繰り返し読むようになったのが懐かしい。
登場頻度は低かったが鞍作鳥が個人的にはとても好きなキャラクターだった。
その後書かれた続編というか後日談である、馬屋古女王は、読むと物悲しくなってはしまうが必読の作品。本作と、里中満智子「天上の虹」「長屋王残照記」「女帝の手記」を読めば、飛鳥〜奈良時代の歴史はかなりしっかりと頭に入るという点でもお勧め。