漂流教室 The Drifting Classroom
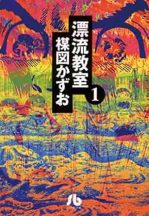
このマンガのレビュー
この世界は過酷で残酷で、全てが好転する夢のような未来ではないけれど、希望はある。子どもたちの強さを信じ、未来への祝福が込められたSFサバイバル冒険活劇。大きな揺れとともに学校が862人の児童と1人の幼児ごと荒廃した未来に転移してしまう。子どもたちはパニックに陥りながらも、生き延びる手段を探そうとするが、ほんの少しの光が見えたかと思えば状況は悪化する一方だ。「第四次世界大戦はこん棒と石で戦われるだろう」と言葉を残したアインシュタインの考えを体現するかのように、状況が過酷になるにつれ槍や斧で戦うようになるのはまるで原始時代。
水と食料、力関係、宗教やパートナーにまつわる争い。荒廃した世界で起きる熾烈な争いは小学生同士ながら社会の縮図だ。こうした争いが人間の原始的欲求で、この状況で子どもの内なるそれが開花したのなら、仲間をつくり助け合い、幼い子は保護し守るその行動もまた人間に備わった本質だと信じたいし、信じさせてくれる。人間は清濁あわせ持つ生き物で、嫌になる時もあるけれど、くさらずに希望を探し続けよう。
荒れ果てた未来世界へ学校ごと跳ばされサバイバル状況に放り込まれた子どもたちに、続々と脅威が襲いかかる。その最初期における最大級の脅威は、本来なら子どもを守るべき大人たちだった。異常事態に際して、先に精神に変調をきたしたのも大人たちだった。そうした描き方に、「子どもであること」にこだわった楳図かずおの人間観が先鋭的なかたちで表出している。
一人の有害な大人を除いて子どもだけの世界になった極限的な状況の中で、学校を国に見立て、総理大臣を選挙で決め、各大臣を任命し、防衛や防疫や食糧確保や発電に取り組む。本作では、そのようにして生き残りを目指す、子どもたちなりの知力や理性が描かれる。そこで主人公・高松翔が次のようなことを訴える。これからの自分たちにとって勉強とは、よい成績をとればいいというものではなく、自分たちの生死に直結してくるものになる。今まで自分たちが学校で勉強してきたのはこのためだったのだ――。
翔が言ったとおり、机上の知識としか思えなかった学校の勉強が、生きるために切実に必要なものとして突きつけられる。勉強の大切さをここまで強烈な迫真性をもって訴えかけるのだから、その意味で『漂流教室』は真に教育的なマンガといえるだろう。
と書いたそばから前言と矛盾するようなことを述べるが、本作は、学校で教わったとおりにしたら危ないことになったり、既存の常識が通用しない事態が多発する。現代に生きる者からしたら、ひどく不条理な世界なのだ。綺麗事ではすまされない子どもたちの残虐性や獣性が露呈する場面も多い。凄惨な殺し合いすら起こる。それでもなお、翔たちはみんなで生き残ろうとすることをあきらめない。物事を理屈でとらえてしまう大人たちには耐えられなかった不条理な世界で、子どもたちは子どもであるがゆえにその世界を受けとめて生き続けようとするのだ。
漂流教室は、未知との戦いではなく「事実をどう解釈するか」を巡る子供たちの戦いの物語です。初めて読んだとき、謎の怪物との戦闘シーンにはさほど心は動きませんでした。しかし、子供同士が殺し合う衝撃的な描写には恐怖を覚え、胸が締めつけられ恐怖したのを今でも覚えています。
主人公のショウは、小学6年生という幼さながらも、明確なビジョンとリーダーシップを持つ少年です。「おかあさん、おかあさん」と泣き叫ぶ姿に心が痛みますが、彼は受け入れ難い現実を自分なりに解釈し、その強さで他の生徒たちを引きつけます。この「強い解釈力」こそが、彼を生存へと導く鍵になっています。
一方で、物語に登場する大人たちは皆「解釈に負ける」存在です。彼らは絶望に囚われ、それが他者へと伝播し、負の感情を連鎖させてしまいます。この状況に抗うのは、ショウのようにリーダーシップを持つ一部の子供たち。彼らは、大人ですら直視できない現実をどう受け入れるか、どのように解釈するかを必死に模索しながら生き抜こうとします。
物語のラストで描かれる解釈は、もはや子供らしさの延長にあるものではありません。しかし、生き延びて強くなったショウたちが紡ぎ出した解釈だと考えれば、それは希望に満ちた結末です。
この作品では、「事実そのもの」よりも「その解釈」が物語の核心にあると感じました。子供的な純粋さ、大人的な合理性、そしてその中間で揺れ動く彼らの姿が織りなす、緊張感あふれるサバイバルホラー。読むたびに新たな発見があり、深く心に刻まれる作品です。
ぜひ、多くの方に『漂流教室』を手に取っていただき、自分なりの解釈を楽しんで頂ければと思います。
ある日突然、学校が未来の荒廃した世界に飛ばされ、命を懸けて生き抜かなければならない子供たちを描いた物語。
主人公・高松翔は、極限の状況下で仲間たちと手を組み、暴力や裏切りに直面しながら、ただ生きる術を探し続ける。物語は、安易に正義や希望を語ることなく、読者に対して生きる重さと人間の弱さを直視させる。
作者は『十五少年漂流記』を発想の源としつつ、連載当時の社会問題であった「公害」や「家族」のテーマを織り交ぜたという。
工業化の光と影が色濃くなりつつあった時代に、未来の荒廃した地球を描き出し、単なるサバイバル冒険譚にとどまらず、深い社会的問題意識を持った作品となった。
また、緻密な画風が、荒廃した未来の風景や恐怖に引き裂かれる子供たちを生々しく伝え、時折、殺伐とした世界の中にも奇妙なユーモアを感じさせる。このコントラストの妙も魅力といえよう。
本作は、ただの恐怖漫画やSF冒険譚に終始しない、人間の生への祈りと命を繋ぐ絆の力を描いた物語である。翔が母親との通信を通じて再び立ち上がる場面は、読者の心に強く響く。母の声に励まされ、翔は諦めず、再び歩み始める。その姿に、母を持つ全ての読者は気持ちを動かさずにはいられない。
筆者は小学生の頃この物語を読み、強烈な恐怖感とともに、主人公とこの世界観に憧れたものだ。自分ならこの世界にどう立ち向かえるのだろうか、と。作者はその後『14歳』という作品で「本作での地球の未来が、なぜ砂漠と化したのか」を描いている。併せて読まれたい。
昨年亡くなった楳図かずお氏の代表作であり、多くの識者の方により様々な視点から作品論が語られている。その意味では本作に関して、筆者が新たに付け加えるような要素は見当たらない。本作に限らず、楳図作品に関して、一言だけ言えることがあるなら「この作品が存在しなかったら、一生の間、絶対に見ることができなかった光景」がそこには広がっているということであろう。正直、常人の頭では到底理解ができないような「とんでもなシーン」や「仰天する展開」も見られ、その強烈さからパロディーの素材にすらなってしまう部分も存在するが、その背後を流れる「とてつもなくピュアで崇高なる想い」の力で、結局は「感動」の坩堝に落とされてしまうのだ。
ちなみに筆者は『神の左手悪魔の右手』の一時期、氏の担当をさせて頂いた関係で、「UMEZZ PERFECTION!」という撰集を出させていただいたことがあった。その中に本作もあったが、楳図作品はどれも長い間に亘って、版を重ねてきたものばかりで、よく見ると刊行された時代時代の要請に応じて、テキストを変更している箇所が多々あることがわかる(もちろん「敢えて当時の表現をそのまま使います」という但し書きを使って、そのまま進める場合もあるわけだがーー)。その時の撰集でも同様のことがいくつかあったが、基本、氏はその修正に対してほとんど反論されたことがなかったのが思い出される。点丸一つにも拘る作家に対して、筆者は大いなる敬意を払うものである(自分もそちら側であろう)。しかし楳図氏は全く違った。あくまで想像であるが、楳図氏はこう思ったのではないだろうか? 「その程度の修正で、自分の作品は微動だにしない」――凄い確信である。