童夢 Domu: A Child's Dream
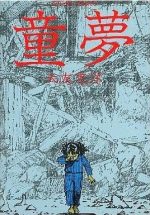
このマンガのレビュー
25人が変死を遂げているマンモス団地。その犯行はいつも広場のベンチで静かに座っているおじいちゃんの超能力によるものだった。さらなる力を持つ女の子が引っ越してきたことで、超能力者同士の死闘が人知れず繰り広げられることになるーーこんな最高にワクワクする舞台設定とプロット、思いついただけで優勝ものだろう。
団地ってなんか怖い。高度経済成長期に次々と建設された団地住宅は、80年頃には老朽化が始まりつつあり、資本主義社会のしわ寄せか自殺のニュースも絶えなかったという。無地の壁にベランダや窓枠が均等に並び、さらにその住棟がコピー&ペーストしたかのように連なる様は、人間を産業の労働力にしてしまったかのような負のオーラが漂っている。
その“現代のお化け屋敷”ともいえる団地を大友は、大ゴマ、時には見開きいっぱいに圧倒的な緻密な線で描く。そこを老人が夜な夜な壁をすり抜け各家庭を覗き見したり、人を屋上に誘い出しては飛び降りさせたりしている。派手な血しぶきも怪物もいらない、湿度の高い恐怖が画面に横たわっている。
物語の後半では夜の団地を二人が宙を飛び回り過激な超能力バトルを繰り広げる。連なるコンクリ住棟の“圧”のなか、老爺とパジャマ姿の幼女がぽつんと対峙しているその構図がとにかくスタイリッシュだ。
超能力を表現するにも、ビームや呪符といった記号に頼らない。壁が円形に凹んで割れたり、遊具が折れたりと、超能力による物理現象のみが写実的に描かれる。昼間の公園で向かい合った二人が人知れず大きな力がぶつけあっている、静と動、不気味さと熱狂が同居したバトルシーンは、時代にとらわれないかっこよさがあるだろう。
私欲を満たすためだけに並外れた力を使い人々を混沌に陥れる老人を、さらに強い力をもつ次世代が利他的な思いから退場させていく、というストーリーも、「失われた30年」と称されるほど経済の停滞が続く今の日本社会に響くものがある。見たい映画に悩んでいたら迷わずこの一冊を読め、と堂々と差し出せる、全方位へのエンタメが詰まった不朽の名作だ。
「大友以前・大友以後」という言葉がある。「80年代ニューウェーブ」というムーブメントの代表的な漫画家、大友克洋が後世に与えた影響を現す言葉だ。
その大友克洋が代表作「AKIRA」を連載する前の1980年から1981年にかけて双葉社「アクションデラックス特別増刊」「スーパーフィクション」に4回にわけて連載され、後に「AKIRA」連載中の1983年に単行本全一巻としてまとめられたのが「童夢」である。
冒頭、この作品のキーアイテムとなる「羽根のついた帽子」(これは「Dr.スランプ」のアラレちゃんの帽子である)を被った男が団地の屋上から飛び降りるシーンからはじまり、続いて捜査に来た刑事たちの登場でサスペンスものと思わせながら、徐々に巨大な団地で繰り広げられるサイキックアクションへと読者は引きずり込まれる。
その舞台となる団地も細密な描きこみで圧倒的なリアリティに溢れていて評価が高いが、団地に住む住人達の人間模様も同様にリアリティある筆致で描かれている事にも注目をしたい。ひきこもりの浪人生、子供を亡くした母親、職を失った父とその息子…
その中で、認知症に似た状態で子供のようなふるまいをするチョウさんと、団地に引っ越してきた少女エッちゃんの2人の超能力者が団地内で縦横無尽に戦うバトルシーンがこの作品の見せ場となっているが、エッちゃんと共闘する「心が子ども」の青年ヨッちゃんや、チョウさんから与えられたピストルで凶行に及ぶエッちゃんの同級生の父の吉川も印象的だ。
そして超能力によって壁に身体が少しずつめり込む描写は従来の漫画表現に無かったインパクトを与えた名シーンとして語り草となっている。
単行本全一巻ながらそれ以上の読み応えがあり、大友作品初心者にもおすすめできる作品である。
かっこよくて背伸びしてでも読んでみたい。
手に入りづらい状況が続いていましたが、
中でも「童夢」は超有名作品「AKIRA」
シリアスなSF、圧倒的な描き込み、
圧倒的な画力と描き込みの細密さは言うまでもないが、改めて読むと、極めて1980年代初頭という時代を描き込んだ作品であるということに気づく。
自殺の名所化する巨大団地、受験戦争で精神のバランスを崩した浪人生、地縁血縁から切り離されて集住する核家族家庭。独居老人、ガス爆発、立てこもり。相互無関心と、日常に変調を持ち込む大事件への暗い歓喜。あらゆる熱が去り、その後に残った矛盾や不合理を整然とした近代建築や制度に閉じ込めて不可視とした時代の風景——のちに「終わりなき日常」と言われたような——が、「子ども」たちによってかき乱され、切り裂かれ、爆発炎上する。退屈を紛らわすかのように人を殺めていく「子ども」もいれば、それを止めようとする「子ども」もいる。だが、その力と力がぶつかったとき、後者もまた巨大な破壊者になるのだ。
平板な風景に慣れきってしまった大人たちには感知できない次元で繰り広げられる、その後の『AKIRA』にも通じるような超能力バトルは、実にハルマゲドン的である。2025年にこれを見ている私たちは、本作に登場する悦子の年頃の「子ども」たちがそののち1990年代に起こしたことを、すでに知っている。だが、この頃の大友克洋がそれを知るわけではない。優れた表現者はいつでも時代の空気を先んじて感得し、鐘を鳴らすのだと感じさせられる。
『AKIRA』の続刊を待ちくたびれていた頃、書店の棚で見かけたのが出会いだ。
正直最初は「『AKIRA』と比べると地味だな」という印象だった。けれど、団地というごく普通の生活空間にこっそり仕込まれた超能力という非日常は、性癖といっていいほど、魅力的で、読むほどに“静かなSF”の底知れない迫力に引き込まれた。
とくに印象的だったのは、いわゆる“壁ドン”のシーン。3331で開催された大友克洋展でも再現されていたあの場面は、超能力を“球体”として描く表現が視覚的にすごく鮮烈だったと思う。それまでにも超能力者が壁を吹っ飛ばす描写はあったけれど、見えない力の形を“丸み”だけで表現する手法は初めて見た気がした。その壁の凹みを見ただけで、こちらも一瞬にして異常事態を理解するから、まさに漫画ならではの衝撃だった。
もうひとつ面白かったのは、社会的には弾かれた弱い立場の人たちが、事件の中心に配置されているところ。刑事をはじめとした“公的な大人”は、ほとんど何が起きているか理解できていない。それが大友克洋らしい社会批評の匂いを帯びていて、「こういう視点で世界を描くのか」と感心した覚えがある。
そして何よりも魅力なのが“団地”の描写。今では団地がエンタメの舞台になることも珍しくないけれど、『童夢』が初出のインパクトは絶大だった。僕の相方の妹尾はずっと団地生まれ団地育ち。ずっと団地を嫌っていたそうだけれど、この作品を読んで「団地がかっこよく思えるようになった」そうである。
ホラーというより、日常が地続きで歪む感覚の面白さ。大げさに怖がらせるわけではないのに、普段の風景が別物に見えてくるあの感覚は、今でいうARグラス越しに世界を見たときのような新鮮さだったと思う。『AKIRA』のようなド派手な超能力戦に比べれば絵としては地味だけれど、そういう静かなSF要素こそが『童夢』最大の魅力だ。
端的に言ってものすごくかっこいいマンガなので、SF&ミステリー好きな方々にはぜひ一度は読んでもらいたい。その上で、東京という都市が戦後どういう変化によって成立して、どう家族の形態は変化してきたのか、ということにも思いを馳せてみてもらいたい。
物語に出てくるのは巨大な団地群。戦後の住宅供給不足を解決するために、各地の里山は開発され、各地の都市近郊に団地が建てられていった。「童夢」は巨大な団地の中で起きる不可解な殺人事件の行方を描いている。
この作品が発表された1980年は、第四次中東戦争が原因でオイルショックが起きた年。それよりも前の1970年、日本は科学技術に大きな期待を持って大阪万国博覧会を経験し、その後、学生運動、経済成長率の停滞による物価上昇、光化学スモッグなどの公害問題を経験した。1974年は、セブンイレブンが豊洲にオープンして、単身生活が急速に一般化していく頃でもある。
戦後の急成長で団地が普及し、都市にサラリーマンとしてお金を稼ぎ、家族を養う核家族が増殖した。隣同士が顔を突き合わせて、どこの子供か一目でわかっていた暮らしから、コンクリートで隔たれた暮らしに変わり、「隣の人は何する人ぞ」状態が生まれていく。
作品では一人で暮らす老人男性に焦点が当たる。団地内に認知症とされる老人男性が住んでいて、誰の仕業かわからない事件が夜な夜な起こる…。姿を見せない犯人を追う刑事の視点で物語は進んでいき、まるでヒッチコックの映画を見ているような気分になる。かつて赤坂憲雄の「排除の現象学」に記されたように「均質の時間によって支配される、主婦と子どもたちの街」が壊される恐怖なのだ。ジワジワと謎解きが進む恐怖、隣人に興味を示さない住民たち。都市という構造への疑念、そしてそれが今でも続いているという危機感を掻き立てられる。
エスパーなど超能力者を含むオカルトブームの真っただ中で「大友ショック」と呼ばれた漫画界における話題の現象を巻き起こした大友克洋先生のサスペンスマンガ全一巻完結作品。
近代日本の暮らしの象徴の一つとなっていた戦後に普及した住宅団地は、少子高齢化社会の減少が可視化され始めた1980年代頃には徐々にゴーストタウン化していく現象を利用し、大友先生は見事に現代日本独特なホラーの舞台として設定することに見事に成功。
普段何気なく見かけている団地を非日常的かつ超自然的なSFホラー系の展開に活かすために完全にイメージを変える手法の一つとして、非常に細かいディテールに満ちた描写により「怖さ」を追求する表現に見えてくる衝撃的な効果は抜群。
マンガという媒体の特徴の一つは、ビジュアルなメディアでありながら映画や演劇と違い、「尺」は決まっていない。それは、つまり、読者が自分の読むペースで物語が進むと思いがちだが、実は均等ではない。アクションシーンと会話シーンでどうしても目を通すスピードの違いはともかく、コマ数やコマ同士の流れ、またコマの内容によっても異なるであろう。本来尺が決まっている実写映画のホラーシーンで感じる恐怖を観客に最大に上げるためには照明、音響だけではなく「ため」の長さもしっかりコントロールすることで、タイミングよく「カタルシス」をもたらし、ドキッと感が増す。大友先生は『童夢』で見事に証明したのは、このような映画的映像文法はマンガのページにも適用できるということ。そしてそうすることによって、ホラー映画のようなペーシングを再現できることになり、読者は話の進行をページめくりでコントロールしているのではなく、マンガ家がページ内のコマの構成で定まっている視線誘導で読者の読むペースをコントロールする結果になるのだ。このような恐ろしい錯覚そのものが、『童夢』の隠れた手品のような魅力であろう。