釣りキチ三平 Fisherman Sanpei
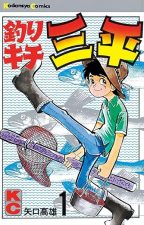
このマンガのレビュー
誕生日が三月三日の主人公、三平三平くんと釣り竿職人の一平じいさん、釣りのライバルであり兄のような存在の鮎川魚紳さんらと共に、日本のみならず世界各地の魚を釣りまくります。魚種の特徴や模様はもちろん、ヒレや口元のかっこよさ、ぷりぷりした体型など魚を手にした時の感動や躍動感がコマから溢れ出ています。丁寧な表現は魚のみならず自然描写からも、矢口さんの自然に対する敬意が感じ取れて胸熱です。キラキラと輝く水面、風になびく草花、まぶしい太陽の輝き、四季の移ろいなど、三平くんといっしょに釣りに出かけたような気分が味わえます。
オススメしたいのは幻の魚「滝太郎」編、潜水艦の「アカメ編」、いやいや海外旅行気分が味わえるカナダの「サーモン・ダービー」編も捨てがたい、と上げるとキリがありません。単行本は60巻以上ありますが、どこから読んでも魅力は堪能できるはず。さらに最終回「涙のブランコ」も必読。未読の人はネット検索などせず読んでみてください。
ページを開くと、しなる竿、三平の伸ばされた手、喜びに飛び上がる体、たくさんの勢いがコマから飛び出してくるのを感じます。そしてその勢いは、美しく描かれた風景の中で一層きらめいて息づいています。釣りが大好きな三平が自然の中でのびのびと魚と対峙する清々しさを、読み手がどこに居てもページのこちらにもたっぷりと味わせてくれます。
釣りというひとつのテーマを柱にしながら、水辺にやってくる人たちとのかかわりも魅力です。一平じいさま、ユリッペ、正治、魚紳さんたち、三平を支える人たち皆が笑ったりふくれっ面をしたり、活き活きと三平の暮らしている世界に連れて行ってくれます。
また、物語には度々、環境汚染や、自然への配慮、伝統的な漁法への取り組みなどが描かれます。真摯に釣りに向き合う三平や周囲の人の姿と、揺れる木々や跳ねる魚の水しぶきの躍動感までもがなめらかな線で描かれることで、釣りのわくわく感も、人間の心の触れ合いも、素晴らしい自然の様子もが調和し、楽しさを持ったまま心に染み入ってくるように思うのです。
地方マンガセレクション①
昭和、平成と釣りを通して様々な問題を提唱してきたこの作品は、令和の時代になってますますその存在価値が高まっています。失われていく地方の風物詩、危機に瀕する豊かな自然環境、釣り人たちに見られるマナーの低下など作品で訴えられた問題は一向に改善されていません。
だからこそ三平の世界は今、この時代に改めて読み継がれなければならないと思うのです。三平が暮らした山と川の美しさ、そこで繰り広げられた魚とのファイトの迫力、人間と自然が織りなす風物の豊かさなどのエピソードはまさに日本の原点そのものではないでしょうか。
令和に生きる若い人たちにも必ず刺さる作品です。今話題の地域の癒し効果、スローライフというコンセプトがこの作品には散りばめられています。釣りマンガというジャンルは日本にしかないということで、そのルーツであるこの作品は今アメリカでも注目を集めています。
矢口高雄は昭和を代表するマンガ家、原作者とも深い関わりがあります。手塚治虫にキャラクター作りを、白土三平に自然描写の技法を、梶原一騎にストーリーの作り方を学んでいます。矢口というペンネームは梶原一騎がつけたものです。トキワ荘の時代を作り上げた手塚、白土、梶原の3人のエッセンスがこの作品が詰め込まれているのです。
トキワ荘の時代には地方を舞台にした作品が多数登場しました。その頃の空気感がたっぷりと詰め込まれたこの作品、地方マンガセレクションの一つとしてぜひ読み返してください。なお三平の世界をリアルで楽しみたい方は横手市増田まんが美術館に行ってみましょう。常設原画展に加えて、当館のコンベンションホールの緞帳「山女魚群泳」の迫力には度肝を抜かれることでしょう。