龍神沼 Dragon God Pond
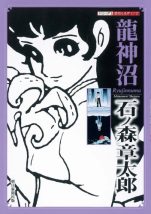
このマンガのレビュー
その後の少女マンガが内面描写を重視したという点で、本作は少女マンガの源泉の一つであり、その表現の方向性を決めた画期的な作品。しかも、石ノ森は『マンガ家入門』の中で本作を理屈で一コマ一コマ、惜しみなく解説した。この点でその後のマンガ家に与えた影響は計り知れない。このころの石ノ森の斬新なカッコよさを、大塚英志氏は、70年代の大友克洋に例えていたが、今となってはこの例えは通じないかもしれない。
かくして、本作は、短編マンガ作品としての完成度の高さ、そしてそれらが言語化されているがゆえに、マンガ家になりたい人が学ぶべき恰好の「教材」としての側面がある。同じ理由でマンガに関わる仕事につきたい人にとっても、古典的なマンガ表現の理解に必須の参照作品だろう。
大塚英志氏は10年ほど前、海外で盛んにマンガ創作のワークショップを行っていたが、その課題はシナリオ化した本作の一部からマンガのネームを作成するというものであった。大塚氏は参加者が描いた各々のネームを、書画カメラでスクリーンに写して添削した。イスラエルやシンガポール、フランスといった国々で、マンガ家志望の学生がシナリオを読み込んで思い思いのスタイルで図像化・コマ割りし、それを「編集者」がアドバイスをするといったやり取りを想像してみて欲しい。私はこのワークショップのフランスでの開催を何度かコーディネートさせていただいたが、十人十色のネームを拝見することが出来てマンガの奥深さを再認識した。大塚さんの試みは『世界まんが塾』という本で詳しく報告されているのでぜひご参照されたいが、一つ例を上げよう。参加者の一人、パリの中学の美術教師サラさんは、ガロというかオルタナティヴ・コミック風の絵柄で、本作ラストの別れのシーンを描いた。大塚さんの前日の講義を聞いただけで彼女は、なんと逆方向の左綴じのコマ割りにも関わらず、本場アメコミなどと違って非常にスムーズに「映画のように」読めるネームを仕上げてきた。本作は洋の東西を越えてマンガの描き方を学ぶことが出来る優れたお手本なのだ。かくもマンガ表現として完成度の高い本作を是非一度手にとって欲しい。
デビューしてしばらくした頃、自分の土台の弱さがどうにも気になり始めた。ストーリーの作り方や絵の描き方を解説した本はいくらでもあるのに、「漫画そのものの描き方」についてピンとくる指南書はなかなか見つからなかった。そんなとき出会ったのが、『龍神沼』が掲載されている『マンガ家入門』だった。
この本の中に収録されている『龍神沼』と、その詳細な解説を読んで衝撃を受けた。「こんなに理詰めで漫画って描いていいんだ!」という実感が、一気に目の前を開いてくれた気がする。それまではどこかで「漫画は、天才が脳内のブラックボックスからひねり出すもの」と思い込んでいたし、僕自身も毎回ガチャを回すような感じで原稿を仕上げていた。麻雀でいえば、配牌の瞬間にあがっている「天和」しか役を知らずに麻雀をやっていたようなものである。
けれど『龍神沼』を題材にした石ノ森先生の解説を読むと、ページ割りからキャラクターの配置、効果線の引き方にいたるまで、「こうすれば読者にこの感情を与えられる」という理屈がしっかり書かれていた。これって今風に言えば「言語化」だ。感性やカンに頼るだけじゃない、再現可能なプロセスで漫画の魅力を生み出す。その考え方が個人的にはすごく性に合った。
もしこの理詰めの漫画づくりに触れられなかったら、僕はとっくに挫折して漫画家をやめていたかもしれない。天才のひらめきを待たずとも、手順を踏んで描けば作品を構築していけるんだと知れたことは、まさに救いだった。『龍神沼』の「見せ方」を徹底的に分析する解説があったからこそ、忘れられない作品、恩義すら感じている作品だ。今でも「どう演出すれば効果的か?」と思い悩んだときは、『龍神沼』を思い出す。
デビューの勢いだけで走り続けていた自分を、しっかりと基礎固めへと導いてくれた作品(と解説)。これがなかったら、今の僕はいないんじゃないかと思う。