漫画家残酷物語 The Harsh Story of Manga Artist
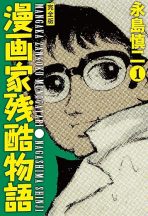
このマンガのレビュー
「なんか古めかしいタイトルだなぁ」と思う人は40代くらいか。もっと若い世代にはタイトルのニュアンスは伝わらないだろう。昔、大島渚という「朝まで生テレビ」で眠くなる時間帯に怒鳴るお爺さんがいて、その監督の出世作『青春残酷物語』(1960年)が元ネタである。この映画は若者のカルト的人気から商業的ヒットへと大化けしたので、やったらめったら「〇〇残酷物語」というタイトルが映画などにつけられた。だが終いには1962年イタリアのフェイク・ドキュメンタリー映画が『世界残酷物語』というタイトルで大ヒット。猟奇的なシーン満載のこの手の映画は「モンド映画」と言われ、70年代に一大ジャンルとなる。ここで変な色がついた。このタイトルがどうもピンとこないのはそのせいだが、本作は当時の若きマンガ家たちに芸術的な自意識をもたらしたカリスマ的作品でなのである。
時代性を纏いすぎた作品が後年あらぬ誤解を受けるのは世の習いで、本作は今ではあまり読まれない作品になってしまったようだ。しかし永島慎二という作家はかなり稀有な存在で、梶原一騎と組んでスポ根マンガ『柔道一直線』を描いてエンターテイメントとしても成功し、『漫画家残酷物語』の続編『若者たち』はNHKで『黄色い涙』と改題されてドラマ化されて(2007年に嵐の主演で映画化も!)、芸術志向の若者だけでなく、広く一般にも感動を与えた。永島は手塚の誘いを受け虫プロで働いた後には、なんと「ガロ」と「COM」の両方に作品を掲載し、寅さんより早く『フーテン』というタイトルの作品を刊行。80年代にすでに米国で翻訳されたユーモアまんが『旅人くん』という作品もある。永島マンガのテイストは多岐にわたり、プロから尊敬された「Musician of musician」なのだ。
同時期に虫プロで同僚であった坂口尚は、兄貴分のように永島を慕い、毎日のように飲み歩いていたという。そんな坂口は永島作品それ自体よりも彼の創作姿勢に大いに影響されたと語っている。おお、これはまるでリアル『漫画家残酷物語』ではないか!
マンガというジャンルは、今や「クールジャパン」政策とされる4.7兆円輸出産業の主要品目となるまでに大きく成長した。しかし、戦前の赤本漫画の時代より、マンガはすでにアート(自己表現)であると同時に、ビジネス(人気商売)でもあるという両方の側面を持っていた。そして、そこに携わる人間(マンガ家)は、決して近いとは言えない両側の崖に足を掛けて、ともすると股裂状態になりながら、創作活動を続けてきたと言える。しかもそれは孤独な作業である。同業者は同じ志を持つ友であると同時に、読者を奪い合う敵でもある。本作の各短編に通底するテーマはほぼこの一点に尽きる。しかも今と比べて、そのジャンルの社会的地位の低さが当時の状況をさらに残酷なものにしたことはあったであろう。そうした状況下で描かれた本作には「本当のマンガが描きたい」「しかし食っていける自信がない」といった、作者の分身たちの股先状態が痛々しいほどのリアルさで描かれている。
永島氏の作品を評して「独特のムードがある」と言われることが多い。片目を白眼にして、その空疎な内面を表すような描写などは独特の感覚を感じるが、決して「雰囲気マンガ」ではない。明確なテーマに向けて、やりすぎと思えるくらいに緻密にプロットを作り込んでいることから、自分の描こうとしているものへの自信と使命感を感じ取ることができる。ただ、その一方で作家本人が本作の登場人物同様に悩み、揺れ続けてきたことは確かであろう。実は筆者にとっての永島慎二初体験は「週刊少年キング」に連載された『柔道一直線』であった。メジャー週刊誌連載で梶原一騎氏とのコンビという、自身のキャリアとしては例外的な作品であろう。この作品がスタートした経緯、その際の本人の談話等は確認できていないが、結局、途中で作画を降板し、別のマンガ家(斎藤ゆずる氏)に交代したという事実は、永島氏が大いなる股裂状態の中でもがき続けていたことの証左であろう。残酷ではあるが、抜けられないくらい魅力的な世界がそこにはあったのだ。