ねじ式 Screw Style
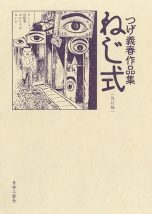
このマンガのレビュー
つげ義春は2020年1月アングレーム国際漫画祭で「特別栄誉賞」を受賞した。『つげ義春全集』の刊行が始まったのはその前年である。フランスでかくも注目を集めるつげであるが実はマンガブームとは別の文脈にいる。おそらく移入の仕方が違ったのだ。欧米ではどうも「ガロ系」作品をオルタナティヴ・コミックス(以下、COMIX)と雑に一括りにしている気がするのだが、実際は因果関係が逆で、ガロ作品などの中からCOMIXっぽいものを選んで出版したので、結果そのように見えているだけではなかろうか。90年代半ばフランスでこの手の作品を出すインディーズ出版社が一定の成功をおさめ、創設・合併ブームが起きた。つげの移入はこの流れに属するのだ。
つげ作品を米国で最初に掲載したのは『マウス』で有名なスピーゲルマンが始めた雑誌「Raw」であり、『紅い花』が 1985年、『大場電気鍍金工業所』1990年である。スピーゲルマンとこの雑誌こそCOMIXの発展に寄与した媒体であり、つげ作品は最初からこのジャンルに入れられていたわけだ。「Raw」はフランスでも読まれており、間は空くがこの流れで2004年に『無能の人』がEgo comme Xという出版社からフランスで最初に出された。仏版『つげ義春全集』を出したのも、エゴがXだという奇妙な名前のこの出版社も日本マンガ専門ではなく、日仏米など世界のCOMIX、グラフィック・ノベルを出している出版社である。この手の出版社のお好みは「自伝的」であるということだ。戦争体験や精神疾患、移民のアイデンティティなど内的葛藤を描く作品が多く、現在ではフェミニズム、LGBTをテーマにしたものも流行りだ。2024年藤原マキの『私の絵日記』がアイズナー賞「最優秀アジア作品賞」を受賞したが、おそらくつげ夫人ということで米国でも同じ文脈で読まれているのだろう。
だが本作『ねじ式』はこの文脈で読めるのだろうか。確かにつげには「私小説」的と言われる作品群があるが、本作を夢と狂気だけに還元して読まない方がいいのではないか。マンガ表現や制作・産業構造、それらに対する批評的スタンスといった切り口も可能なはずで、実際に日本では本作を読み解こうと様々な文章が書かれてきた。だから本作を未読の方は頭をまっさらにしてまず読んでみて、次に本作の謎が気に入ったら文献を駆使して考察を深めてみて欲しい。
本作の読みの国際的なギャップの存在が、我々が海外の日本マンガ読者とではなく、海外の海外マンガ読者との対話を深めるための重要なカギとなるのかもしれず、この対話は日本マンガの未来に寄与するかもしれない。日本で本作が多くの人に読み返され、海外の同好の士と議論できる日が来るのを待ちたい。
『ねじ式』を読んでいると、悪い夢の中に入り込んでいるような錯覚に陥る。物語としては「ある男が、腕のちぎれた血管を治してくれる医者を求めて漁村をさまよう」だけの話で、大きなドラマもストーリー性もない。荒波の上の真っ赤な空に浮かぶ巨大な飛行機の影、立ち並ぶ目医者の看板、漁村の家屋と家屋の合間を縫うように侵入してくるSL機関車……数コマごとに奇景が現れる上に、登場人物たちが交わす言葉はとても対話が成立しているとは思えない。さらに脈絡なくグロやエロが差し込まれる。不条理で、不気味で、刺激に満ち溢れている。
同時にこの奇譚には戦後日本のノスタルジーとブルースが漂っており、どこか他人のものとは思えぬ寂しさも抱いてしまう。超写実的に描かれる漁村の木造家屋、七輪や機織り機といった民具。本作のモデルは千葉県の外房・太海だそうだが、つげ義春は地方の温泉地や里を旅し、資本主義社会に取り残された人々の営みを愛し、その風土を画面に落とし込んできた作家だった。だからこそ描きうる唯一無二の奇景のコラージュ、戦後の悲哀が織り込まれた”不思議の国のアリス”が『ねじ式』なのだと思う。
タイパ、コスパが重んじられる今の時代を生きていると、これほどまでにナンセンスな展開をこれほどまでの重厚な絵柄で描く作品はもう現れない気がしてくる。『ねじ式』は作者が締切間際にやけくそになって、ラーメン屋の屋根の上でみた夢を描いたものだというが、つげは他にも様々な短編で夢をそのままマンガにしたり、「道理や約束事をあえて無視した作品を描いたりしてきた」と明らかにしている。世の理、常識から徹底的に離れんとする斜に構えた態度、世捨て人としてのスタンスが、この孤高な作品を生んだのも間違いない。
名作の証のひとつとして「パロディにしやすい作品」というのがある。
人気や知名度や評価が高いからこそパロディはしやすく、つげ義春の代表作「ねじ式」もこれにあてはまる。
「ねじ式」は1968年に青林堂刊「月刊漫画ガロ」の五月増刊号「つげ義春特集」で発表された短編作品である。それ以来、手塚治虫、鳥山明、赤瀬川原平、江口寿史、はてはポケモンにまで、扉を含めてわずか23ページしかないこの作品はパロディ化されている。
「ねじ式」は漫画評論家から「芸術漫画」と評価され話題を呼んだが、作者のつげ本人は1976年発行の小学館文庫「ねじ式」のあとがきで「芸術作品だとさわがれたのだが、ラーメン屋の屋根の上でみた夢なのだから、およそ芸術らしくないのだ」と半ば自嘲的に綴っている。
そう、この「ねじ式」は当時、水木しげるのスタッフだったつげが中華料理店に棟続きのアパートに住んでいた頃に見た夢が元になっている。
「夢」を作品化しただけあって「ねじ式」のストーリーの全体を簡潔に説明するのは難しい。
海水浴に来ていたうつろな表情の主人公の少年が「メメクラゲ」という謎のクラゲに左腕をかまれたという独白からはじまり、切断した血管を右手でおさえながら医者を探し不案内な町を徘徊する…というのが基本的なストーリーだが、その徘徊する道のりで出会う人物や風景に一貫性は無く、まさに他人の夢をみせつけられている様な不条理な感覚に襲われる。
そのリアルな筆致で描かれた人物や風景の多くは、当時のカメラ雑誌に掲載された写真家たちの写真を元にしていた事が現在では明らかになっている。
つまりストーリーは「夢」であるが、舞台は「現実」であるという事になる。夢と現実の融合、それが「ねじ式」という作品の大きな魅力なのだ。
「芸術漫画」のレッテルはともかくとして、短編漫画史上最高の名作である事は間違いないだろう。
「まさかこんな所にメメクラゲがいるとは思わなかった」
左腕を押さえながら、海から岸へと向かって来る「ぼく」。たまたまこの海岸に来てメメクラゲに噛まれて静脈が切断され、真っ赤な血がとめどなくながれて「死」を感じながら不慣れな土地で医者を求めて歩きまわる。
劇画的表現、流れる様に様々な風景が目の前で転換し、物語が繰り広げられていく。漁村の人達の無関心や話の通じない様、隣町を目指す為の線路、狐面の少年が運転する機関車、風鈴の音、隣町ではなくまた元の町へ戻ってしまう車窓、目医者ばかりの通り、金太郎飴ビルと「生まれる前のおッ母さん」、女医との出会い、ねじで止められたシリツ(手術)、夢でも見ている様に不安定で退廃的な場面がグルリグルリと回りながら最後には目的が成し遂げられている。
何年も前、友人達と千葉県の太海漁港へ旅に出た。少しでもこの一コマ一コマを見出したくて町を歩いた。別件だが「やなぎ屋主人」のモデルになった長浦の「よろずや」へも行った。特にモデルになっていない街角でも偶に「つげ漫画に出て来そう」と足を止める事がある。この漫画を読んで仕舞うと、物語も風景も脳みその中に「ふぃ」と入って残るのだ。
あまりに多くの評論を生んだ作品ゆえに取り上げることが憚られたが、今回の機会に(短編であることもあり💦)改めて読んでみて、やはり心がざわつくものを感じてしまった次第である。作家本人も「夢が元になっている」ということらしいが、多くの方もそう思うように、筆者も「自分が見たことのある夢のシーン」の断片が散りばめられているような錯覚に囚われてしまう。特に筆者はテツ(鉄道マニア)ゆえに、かつては頻繁に鉄道や線路が登場する夢を見ることがあった。しかも、ご想像通り、好きな趣味であっても、夢になるとなぜか楽しいものではなく、大抵は踏切で動けなくなるような「悪夢」の方が多かった。たまに蒸気機関車が機関区に集合したような嬉しい光景が出てきても、そのうち「ああ、こんな景色、本当はもうこの世にないんだ」と気づいて、泣きそうな面持ちで目を覚ますことになった。そうした筆者からすると、本作に出てくる数多く鉄道の描写は、悪夢というか、取り返しのつかない光景というか、そんな想いで否応なくゾクゾク来るものとなっている。
「なんて歩きづらい道なんだろう」と主人公が歩く、超望遠で捉えたようなグニャグニャの線路、ダージリンヒマラヤ鉄道よりも狭い路地を抜けてくる蒸気機関車、かつての阿里山森林鉄路らしきシェイ式機関車の炭水庫になぜか窓を開けて佇む主人公――どれもやはり、自分がどこかで見たことのある「悪夢の中の鉄道」に思えてならない。そして、一生忘れることのできないマンガの風景でもある。