アシュラ Ashura
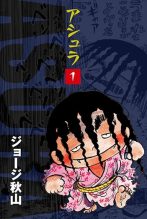
このマンガのレビュー
「アシュラは生まれてこない方がよかったギャ」。金持ちの散所太夫と妾の間に生まれ、狂った母親に殺されかけながらも生き残ったアシュラ。幼くして人を殺し、人肉で飢えを凌ぐことしかできず、まさに生き残るために手段を選ばなかった彼が簡単な言葉を覚え始めたころに叫んだこのセリフが重い。
ジョージ秋山が『銭ゲバ』でも描いた人間の美醜(それは決して表面的ではない)について、『アシュラ』では舞台を平安時代の飢饉に移し、よりプリミティブな世界観で描かれている。しかし、その過激さゆえに、同作が掲載されていた当時の『週刊少年マガジン』は神奈川県で有害図書指定され、社会問題にまで発展した。門を曲がればポリコレにぶつかるくらい社会的に「表現」に対する取り締まりが強まる昨今では、こうした表現はいくらメッセージを宿していたとしても編集部の検閲でストップがかかるだろう。それでも、かつてこうした表現が漫画でなされていたという事実は、漫画の懐の深さを思い出させてくれる。それにしても、こんな過激で前衛的な作品が掲載されていたのが”少年”マガジンというのが愉快である。
平安時代末期。飢餓に苦しむ人々の中には、死が目前に迫ってもなお互いを思いやり食料を分け合う者がいる一方、極限状態に置かれたときには目の前のものを食料と認識し、結果としてカニバリズムに至る者もいた。食人という手段で人間としての尊厳を失うことで生き延びたとしても、救いのない運命が待ち受ける中、「悪を行えば地獄、善を行えば極楽に行ける」という教えさえ虚しく響く世界。「そんなことは迷信だ。生きているうちが地獄だ」というこの世界を生きるものの感情が代弁される。生きていることそのものが地獄だと叫びたくなるような現実が、冒頭から圧倒的な迫力で描かれる作品が「アシュラ」である。
当作品の主人公のアシュラは、法師や若狭からどれだけ説かれても、憎むことで、殺めることで自らをより苦しめていく。殺したいほど憎みながらも、殺めた後に涙を流し、人間らしさを爆発させるアシュラ。その葛藤が深く描かれる。
「生まれてこなければよかった」というセリフを子どもたちが繰り返す絶望の世界で、孤児たちは破天荒で危険極まりないアシュラのリーダーシップを未来への希望と感じてしまう。絶望に満ちた世界の中で、アシュラという存在が微かな希望を象徴している。そんな本作は、読む者に生きることの本質を突きつける重厚な作品だ。
「アシュラ」を人に勧めることは難しい。「アシュラ」の内容は衝撃的である。その「衝撃」を中心に語りたくなるのだが、すると作品の本質から逸れてしまう。
「アシュラ」はジョージ秋山が1970年『少年マガジン』で発表した作品だ。主人公アシュラは、平安末期、飢餓や疫病の蔓延する中、最低限の人間性すら失ってしまった母から産み落とされる。辛うじて命を繋いだアシュラは「自分など生まれてこなければ良かった」と悩みつつも、生き延びるために殺戮と収奪を繰り返す。そんな中、アシュラは、憐みと愛情を注いでくれる若い女性や、人倫を説く法師などと出会い、自らの生きる意味や生き様を模索していく。
「アシュラ」の絵柄は、今日の観点からすれば、描かれる世界観にまったく見合っていない。「アシュラ」の物語の冒頭は、飢餓の果てに荒廃した村が描かれる。死体にはカラスが群がり、蛆が湧き、白骨化していくのである。凄惨な場面であるが、人の姿は古典漫画的なデフォルメがされて、どこか記号的である。美しく心地よい絵柄では決してない。しかし、それは、内容に対比すると「救い」であり、子どもの心にストレートに届く効果があるようにも思える。
「アシュラ」は、面白おかしい話でもなく、読んでスッキリと爽快な気分になるものでもない。万人に勧められる作品ではなく、実際、掲載された『少年マガジン』が有害図書に指定されたりもした。しかし、キレイな話ばかりを見ていても世の中がキレイになるわけでもない。苛酷な現実が存在しうる以上、人はその事実を咀嚼し乗り越えていかなければならない。それは多くの人が「アシュラ」を読み、そして語り継ぐことで初めて達成できるだろう。「アシュラ」のような作品が半世紀以上前に、広く公開されていたこの「表現の自由」から後退してほしくないなと願っている。
餓死寸前の少年は、平然と人を殺し生きるためだけに人肉を食い続けた…。主人公の「グギャア」という叫び声、醜い容姿で人を傷つけ、生まれてこなければといいながら生への執着を捨てきれない。この究極のマンガでに小学生の自分は震撼したのを強く覚えている。
1970年に連載開始後に『週刊少年マガジン』で連載された同作は「人肉を食べ、我が子も食べようとする母親」というとんでもないものを描き、神奈川県で有害図書指定、社会問題に発展。それでも当時社長の野間省一は自らの責任において連載を断行している。凄いのは本作が2012年になってアニメ化しているという点だろう(『銭ゲバ』は2009年にドラマ化)。キャッチコピーは「眼を、そむけるな」。この事実だけでも、保守的と言われる日本の出版・映像業界がいかに「冒険をしてきたか」という証明にもなる。
人はいかなる状況において親であることをやめ、獣となるのか。そして獣に育てられた者は、どうやって人性を取り戻すことができるのか。ジョージ秋山はギャグマンガ家としてデビューしておきながら、『銭ゲバ』と『アシュラ』という2つの問題作を発表し、人間の善悪やモラルを問おうとした。単なる嗜虐趣味ではない。食人は遭難・飢饉など社会から孤絶した際に究極の選択で、スペイン画家のゴヤが1820年前後にローマ神話から描いた「我が子を食らうサトゥルヌス」などでも取り上げられる、人類の避けがたい暗黒面だ、生半可な遊び心でできることではない。秋山ジョージの評判は大いに傷がつき1971年に一時引退、日本一周の放浪の旅に出ている。
1970年代は公害問題とオイルショックで「科学の時代」を見直そうと顧みられた時代でもある。当時の出版界が、マンガそのものが有害図書とされていた時代でも(『鉄腕アトム』すら焚書されていた1950年代!)歩みを止めず、こうした作品を出版し続けた「覚悟をみせた」意味でも象徴的な作品である。国によっては死刑すらありえる出版テーマを許容した当時の日本の出版界の受容性にリスペクトがとまらない。現在連載中の『ドラマクイン』(市川苦楽・著)にも同作と近い“異常性”を感じている。