Dr.スランプ Dr. Slump
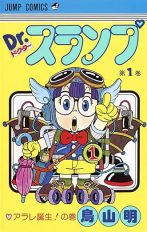
このマンガのレビュー
日本には御手洗いを表す言葉が数多あってトイレ、お便所、雪隠、かわや、はばかり、閑所…etc。
また”レコーディング”…音入れとおトイレの洒落になっていたり、市外局番が045…おしっこという語呂合わせから御手洗いへ行くことを”横浜”なんて言う業界もあるそうだ。
作中で千兵衛博士はあらゆる発明をする、Dr.”スランプ”と言われながらもその手腕は凄腕!時空を自由に移動できる”タイムスリッパー”や、「ドラえもん」の”ビッグライト”と”スモールライト”の機能を併せ持つ”デカチビ光線銃”、そしてもちろん”アラレちゃん”も発明のひとつだ。
しかし!ありとあらゆる発明品のなかで千兵衛博士でも作れなかったものがある。それはこの世界の創造主・鳥山明先生の手によって創られた。いや、捻り出された。
そう、僕が考える「Dr.スランプ」に於ける最大の発明は”うんち”だ。
鳥山明先生が考えたソ○トクリーム型のうんちは今やDr.スランプという作品の範疇に納まらない。
他作品に於けるうんちの作画表現では当たり前のようにあの形(同ジャンプ作品の「キン肉マン」のベンキマンの頭上うんちetc)。昨今ではスマートフォン”うんち”と入力すると予測変換の欄にあの形で絵文字まで出てくる始末だ。
日本だけでなく、世界に於けるデザインに革命を起こしたのはアラレちゃんでもなく、孫悟空でもなく、”うんち”だ。
またこの作品はとにかく隙がない。
物語の進行に関係のないペンギン村のモブたちの発言、機械のデザイン、さまざまなネーミング、落語やコントが元ネタであろうウケどころに至るまで鳥山明先生の引き出しの数々、使い方は足元にも及ばない。
きっと自分がリアルタイム読者であったら、更に理解の及ぶギャグシーンもあるんだろうと思っている。
ちなみにアラレちゃんの喋り方が「ら抜き言葉」のキッカケなんじゃないかと、密かに推測している。
では、ばいちゃ!
鳥山明先生が天才であることを世の中に証明した作品。ドラゴンボールがなかったとしても、Dr.スランプだけで鳥山明先生は天才であることはまごうことなき事実である。Dr.スランプで鳥山明は完成したと思う。見たことがない方向けに簡単に紹介すると、ペンギン村に住んでいた発明家の「則巻千兵衛」は、ある日天才であるがゆえに人型ロボットの「則巻アラレ」を発明する。ただ、アラレは他の人から見るとまったくロボットに見えないため、ペンギン村で学校に通うことになる。生まれたばかりで常識がなかったり知能が低いような行動もしたり、ロボット特有な動きもしつつ、村に馴染んでいく。ドタバタギャグコメディマンガである。ただ、Dr.スランプも1話完結型のギャグパートもあれば、複数話にまたがって話が続くケースも有る。特に、則巻千兵衛のライバルとして現れる「ドクターマシリト」が作る悪のロボットたちとの戦いは見応え抜群!この頃からドラゴンボールの原型があることがわかるのである。ギャグ中心の中でも微笑ましいラブロマンスもあり、キャラの成長もあり、軽い気持ちで安心して、笑いながらマンガを読みたいときにおすすめの一作である。
最も強いマンガキャラクターは誰か?それは範馬勇次郎でもケンシロウでもなく「アラレちゃん」なのではないでしょうか。キーン!と走ればマッハ3。ペガサス流星拳のマッハ1を上回ります。ほいっと拳1つで「地球割」はワンパンマンも叶いません。「んちゃ砲」も超サイヤ人と互角の勝負。。。とにかく「むちゃんこつおい」んです。
自称天才科学者の則巻千兵衛が生み出した人間型ロボット、アラレちゃんを中心に描かれたパワフルコメディは、ガッちゃんやスッパマン、ニコチャン大王など、個性豊かなキャラクターたちも大活躍。魅力はなんといっても、鳥山ワールド全開のポップでバカバカしいギャグ。ドラゴンボール超やDAIMAの魅力の源流がここにあるとも言えます。そして絵の巧さ。シンプルかつ、丸っこい線で描かれる一コマ一コマはグッズやポストカードにして飾りたいくらいうっとりしてしまいます。よく見てみるとトーンもほとんど使わず、ペン一本で描いている所がまた惚れ惚れ。ペンギン村はダサくてド田舎、いつもドタバタ、ハチャメチャだけど、人も動物もロボットも宇宙人でさえも普通に受け入れてくれちゃいます。そんな魅力が支持されて、世界中を虜にする鳥山ワールドを堪能してください。
『Dr.スランプ』の登場はカルチャーショックだった。当時小学生だった私は「なんだこの絵のうまさは! このかわいらしさは! このオシャレな感じは!」と目を見張るような鮮烈な印象を受け、その絵柄を見たとたん虜になった。今読み返しても当時の衝撃は裏切られない。ほれぼれする画力と画風である。
そんな卓抜な絵柄で描かれるスラップスティックで奔放なギャグの面白さにも魅了されるばかりだった。作中で炸裂するギャグの主な発生源であるアラレちゃんの魅力は絶大。その天真爛漫さ、好奇心の旺盛さに底抜けの楽しさと笑いを授けられる。そして、地球を割ってしまえる無双パワーの痛快なこと!
アラレちゃんたちの暮らすペンギン村は、犯罪者や侵略者がよく出るし騒動だらけなのに、住民たちはみんな実に大らか。人間が住むだけじゃなく人間のように話す動物や天体がいるし、怪獣やら何やら不思議な生物もわんさかいて、自由で牧歌的なワンダーランドの様相を呈している。『Dr.スランプ』は、そのキャラクターからも作品の舞台からもイノセントな魅力があふれているのだ。
メタ発言・メタ表現の宝庫でもある。作者が作中にしょっちゅう登場することをはじめ、似た顔の美女しか描けない作者の弱みにつけ込んだ話があったり、今まさにアラレちゃんのいるページをアラレちゃん自身がハサミで切り取ったり、今このページを開いている読者の姿を写真に撮るなど、多種多様にメタな遊びが繰り広げられる。
それまでの多くの少年・少女マンガでは地味な脇役に甘んじがちだった“眼鏡キャラ”をオシャレな存在に押し上げたのも本作の功績だろう。アラレちゃんは「あの眼鏡かわいい! 私もかけたい!!」と読者に思わせるファッションリーダーになったのだ。それもまた革新的な出来事だった。
「Dr.スランプ」との出会いは小学校中学年、近所の床屋の本棚で。毎回繰り広げられるドタバタ劇やギャグの応酬に即座に心打ち抜かれ、床屋から家に帰るやいなや、あるだけの小銭をかき集め近所の本屋でコミックを購入した。
鳥山作品の「キャラクター」はどれも素晴らしいのだが「空間設計」が見事だと思う。「ドラゴンボール」の天下一武道会のステージ上で繰り広げられるバトルはいつまでも飽きさせないし、宇宙船に乗ってナメック星にたどり着いた時のワクワク感は忘れられない。(「SAND LAND」の荒涼とした砂の惑星や「COWA!」の不気味で愛らしい岬など挙げだしたらきりがない)
もちろん「Dr.スランプ」も素晴らしい。小学生だった僕はアラレちゃんと共にみどり先生のいる学校へ通い、放課後はあかねちんと喫茶Coffee Potで寄り道したり、不時着した烈津號(れっつごう)に住む摘姉弟に会いに行ったり、則巻博士の研究所に行き発明をおねだりしたり…とペンギン村を駆け回る空想をした。初連載でこんな世界観を創ることのできた鳥山明、恐ろしい…。
「Dr. スランプ」はグローバルな作家鳥山明の最初の連載作品でありその後の方向性を決定づけたものであるが、連載を通した作風の変遷のなかでいくつかのターニングポイントが見て取れる。
本作は自称天才科学者の則巻千兵衛博士と彼が作ったアンドロイドのアラレによる「博士と助手」のSFコメディ的フォーマットを取っており、アラレを含む千兵衛の発明するガジェットが巻き起こすドタバタ劇を描いている。連載初期はバタ臭さの強い特徴的な絵柄でアラレの等身も高めに設定され、アラレが主人公となっていながらも千兵衛が物語展開のキーパーソンとして描かれていた。オリジナル版単行本の1巻後半からアラレの等身が次第に小さくなり、千兵衛に対する冷静で毒のあるボケ・ツッコミ役から幼児性のある天然キャラに軌道修正がなされ、「とつげきアラレちゃんの巻」(オリジナル版第2巻)あたりでスタイルの定着をみた。千兵衛もモシャモシャ頭のマッドサイエンティスト的風貌から短髪の「お父さん」的スタイルになり、ガッちゃんの登場もあわせてポップなファミリードラマとなり、当初の毒がかなり薄れた。
本作のファミリードラマ性は千兵衛と山吹みどり先生との結婚のエピソードによく表れている。アラレとガッちゃんの世話に手を焼く千兵衛の姿を見て目を細める山吹先生のコマの次のページで、大ゴマで描かれる結婚式という展開は、連載当初の毒を交えたSFコメディからの決別を象徴しているように思える。この目を細める山吹先生の表情もそれまでに彼女が全く見せたことのないものであり、連載当時に目にした際、違和感を覚えたことを記憶している。
アラレのピュアな主人公像は「Dragon Ball」に引き継がれ、ファミリードラマ的要素は少年ジャンプのいちフォーマットとなったが、鳥山があの時捨てたものが今続いていたらと、つい仮定法過去完了に思いをはせてしまうのである。
1976年集英社に入社した鳥嶋和彦が1978年に原稿を持ち込んだ元イラストレーターの鳥山明と出会い、3年の共同作業と500ページのボツ原稿の末に生まれたマンガが1980年に始まる『Dr.スランプ』である。本作は「5年目のマンガ嫌いの新人編集者とデビュー後3年目で初連載、マンガを描いたことのない漫画家の作品」という意味で異例中の異例であり、それでありながら1981年末の第6巻は「初版220万部」と当時ジャンプ歴代の新記録を樹立する(『キン肉マン』の1979年160万部を破った)。
とにかく「異色」だった。ロボット、しかも女の子が主人公。ヒーローものと思いきや、ギャグでポンコツな登場人物も多い。バトルは強いが、別に勝つことが目的でもない。かといってギャグ路線にしては丁寧に描かれた絵と、登場するマシンも世界設定もとにかく書き込まれている。マンガがどの方向に向かうかを模索していた時代に、「とにかくオシャレでクールな、若者文化を代表するマンガ」として新しい目線を獲得していった本作は1980年代の急激に多様化し、マンガが文化の旗手となっていく黎明を開いた。
各産業にとって「当たり前」を常に壊していくのはよそ者、若者、バカ者の特権である。ジャンプを「天下のジャンプ」視しなかった2人だからこそ、できた。鳥嶋氏はのちにこう語る。「「アニメにするとキャラクターがすり減る」って編集部の人間が平気でいってましたからね。ジャンプの300万部だって視聴率にすると3%ですよ。それより『Dr.スランプ』はアニメだと視聴率36%で10倍以上の人が見ているわけです。本当に人間を広げているのはどっちなんだという話ですよ。だから僕はアニメに積極的に関わっていきました」(『エンタの巨匠』2023)
驚きはこんな大人気作をたった5年で惜しげもなく連載終了とし、その後マンガ史を変える『ドラゴンボール』を開始したことだ。マンガ・アニメ・ゲーム・玩具すべてでDr.スランプの世界を味わい、推したのだ。